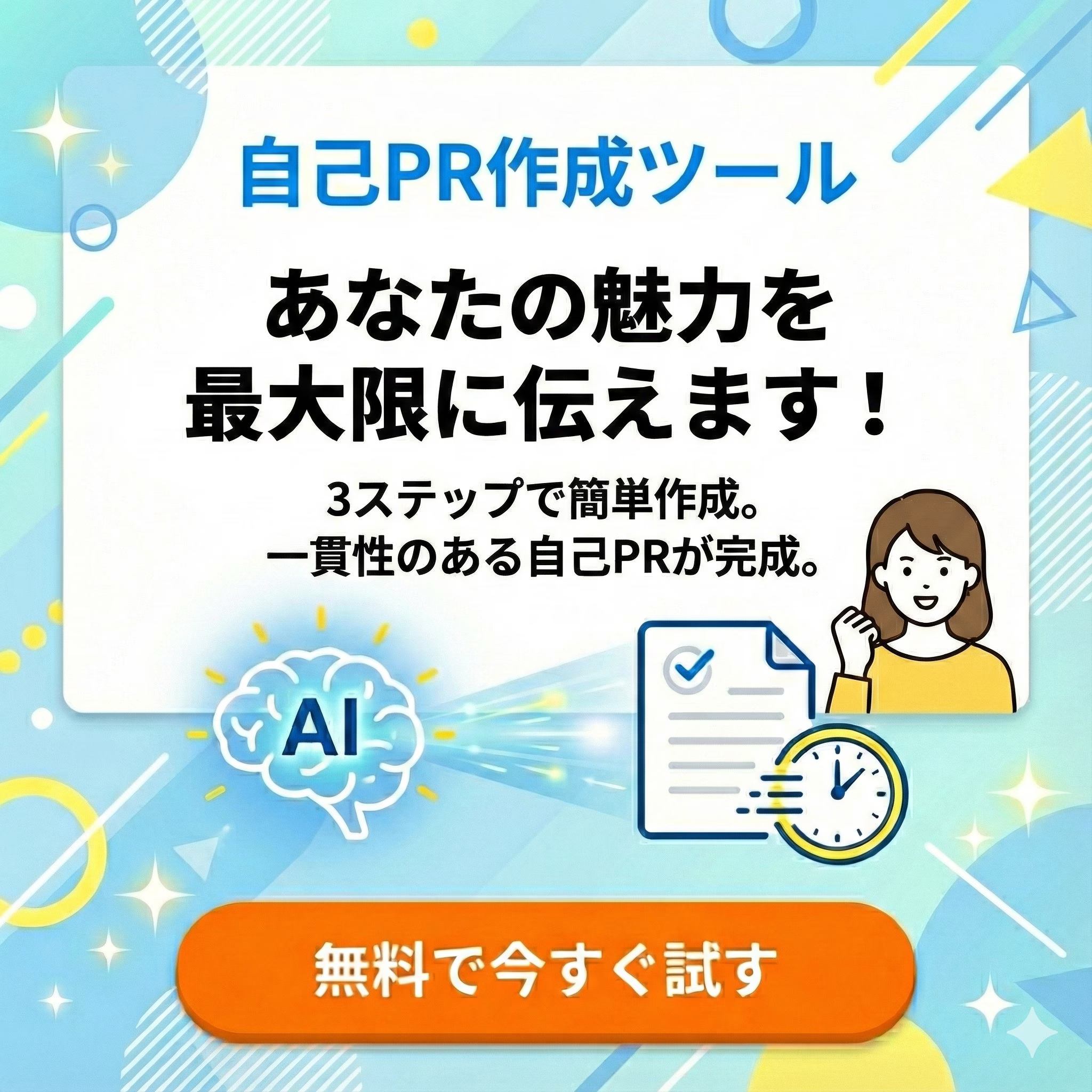【不動産業界研究|2023年度最新版】ESの書き方から面接対策まで徹底解説!
公開日:
最終更新日:

「不動産」と聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?
住宅メーカーをイメージする人もいれば、賃貸の仲介やマンションの建設など、人によって思い浮かべるものは異なると思います。
そもそも「不動産業界」とは、「土地」と「建物」を扱う業界のこと。
大きく分けて3つの事業に分かれており、仕事内容は多岐に渡ります。まずはどのような業界なのかをしっかりと理解することが大切です。
この記事では「不動産業界」に焦点をあてて、採用動向やエントリーシート、面接対策なども詳しく説明していきます。
具体的な業務内容や主要企業の特徴を理解した上で、自分には何が向いているか、どのように働きたいかイメージしながら業界研究を進めていきましょう。
不動産業界の筆記試験対策・攻略法

不動産業界の筆記試験はSPI、玉手箱が多く用いられています。
2021年卒の就活は新型コロナウイルスの影響で、従来ならテストセンター方式やインハウス方式を採用していた企業が、自宅受験型のWebテスティング方式に急きょ変更するなど今までと異なる対応をした企業も多かったようです。
テストの形式や種類そのものを変更する企業もあるため、過去の実績が必ずしも反映されるとは限りませんが、それでも過去の実績から傾向をつかみ、効率よく対策を進めておくことが大事です。
経済の先行き不安や、企業業績の減退によって、就活も売り手市場から買い手市場に移っていく傾向にあります。
買い手市場の時は、企業の採用方針が保守的となり、早期に且つ確実に仕事がこなせる人材を求めます。
そのため、ここ数年以上に能力検査・適性検査は重視される傾向にあると考えられます。早いうちから試験対策にも取り組みましょう。
不動産業界の面接対策・攻略法

面接の回答では「質問の意図を理解した上で答えること」が重要です。
面接官の質問には必ず何かしらの「意図」があります。
十分にリサーチをして「回答の準備」をしておき、面接官が「その質問から何を読み取ろうとしているのか」、「重視しているポイント・知りたがっていることは何か」を理解して返答することを心がけましょう。
不動産業界でよく聞かれる質問と回答のポイントを紹介していきます。
- 売れ残った物件を売る方法は何か
- 不動産の販売においてSNSやインターネットをどう活用するか
- 不動産業界に入るために努力したことを教えてください
- 不動産業界の展望について
- 興味のある商業施設を教えてください
上記は業界を志望する際は優先的に対策しておきたい質問になります。
どの企業の面接においても質問される可能性が高い項目になるので、それぞれ詳細に答えられるように準備しておきましょう。
この他にも、「学生時代に頑張ったこと」や「自己PR」など一般的な質問についても対策しておきましょう。
本記事では「売れ残った物件を売る方法は何か」、「不動産の販売においてSNSやインターネットをどう活用するか」、「不動産業界に入るために努力したことを教えてください」について回答のポイントを詳しく解説します。
「売れ残った物件を売る方法は何か」
この質問で面接官が知りたいのは、「発想力」と「問題点を見極める力」だと考えられます。
物件が売れ残るということは、何か特定の「売れない理由」があるということです。
立地なのか、内装なのか、または間取りが原因ということも考えられます。
この質問での回答では、考えられる様々な原因を例に挙げて、解決策とセットで伝えるように意識するといいでしょう。
ポイントは次の通りです。
・考えられる原因を複数挙げる
・それに対する解決策を述べる
上記の2点を軸に具体的に回答できれば、好印象を与えられるでしょう。
例えば、「子育て世代の家族向け」の住宅が売れ残った場合、「周辺の治安が悪い」や「学校からの距離が遠い」、「通学路の交通量が以上に多い」など様々な原因が考えられます。
こういった原因に対して、「周辺の環境を整備する」か「物件を改装して対象顧客を変える」といった改善策を示せるような回答を心がけてみてください。
「不動産の販売においてSNSやインターネットをどう活用するか」
この質問で面接官が知りたいのは「流通における思考力」だと考えられます。
このような質問は、「不動産流通」に関わる企業の面接で出題される可能性が高いと考えられます。
近年の物件探しの現状を見ると、ポータルサイトやアプリにおける物件探しでは「写真」を重視するユーザーが約7割をしめています。
こういった動向を例に挙げて、SNSにおけるマーケティング戦略の案を次のような順で回答してみましょう。
・SNSやネット利用者の動向を例に挙げる
・それを活用するアイデアを具体的にアピールする
例えば、現在のユーザーが「写真重視」であることを踏まえて、物件の拡販に利用するSNSサービスを「画像や動画が主体のサービス」に絞るなど、動向をうまく利用できるようなプラットフォーム選びも1つの策として有効でしょう。
物件を探す利用者の判断材料や基準に「上手くアプローチできるようなSNSを選ぶ」という軸で回答してみてください。
「不動産業界に入るために努力したことを教えてください」
この質問で面接官が知りたいのは、「目的のために努力できる人間かどうか」、「何が必要か見極める力」だと考えられます。
まずは、この質問を受けた際に何か努力したことを答えられるように、自信を持てることを最低1つは積み上げておきましょう。
これについては特定の正解はありませんが、自信をもって「頑張った」と主張できる取り組みをしておくことが重要です。
回答のポイントは次の通りです。
・努力したこと取り組みについて自信をもって主張する
・なぜその取り組みを頑張ったのか理由を伝える
重要なポイントは、その取り組みを頑張った理由を明確に、論理的に伝えることです。
目的達成のための努力は、「がむしゃら」ではなく「論理的」である必要があります。
「とにかく頑張る」という精神力は求められますが、「どんな取り組みをするか」は明確な根拠をもって決めることがとても大切です。
目的達成のために必要な取り組みを見極める力をアピールするようにしましょう。
以上、各質問の回答ポイントと対策について解説しました。
面接対策をする際は「自分が面接官だったら」という視点を持って考えてみると、必要な対策が見えてきます。
リサーチで得た情報をもとに、想像力を働かせながら業界研究を進めてみてください。